こんにちは、兵庫県加古川市・播磨町で学習塾「ニードモアアカデミー」を運営している三浦です。
ChatGPTをはじめとする生成AIの登場によって、学習環境は劇的に変化しています。
今回のポッドキャスト「ニードモアの聴く塾便り」第31回では、AI時代に学び方がどう変わるのか、そして私たち塾講師の役割はどう変化していくのかについて、具体的な事例を交えながら語り合いました。
全2回シリーズのPart1となる今回は、AIによる学習革命の実態と、これからの教育に求められるものについて詳しく解説します!
AIがもたらす学習速度の革命
驚異的な上達スピードの変化
まず最初に、非常に印象的な事例をご紹介します。
中学生のプログラミング学習を観察し、学習速度をデータ化した研究があります。その結果は驚くべきものでした──数年前と比べて、現代の中学生の上達スピードが比べ物にならないくらい速かったのです。
その秘密は何だったのか?
答えは「ChatGPT」です。この中学生たちには、学習にChatGPTが与えられていました。
従来であれば、プログラムが動かなくなったとき、バグが出たときに1週間、2週間と詰まっていたような問題が、ChatGPTに聞けば一瞬で解決されていくのです。
実際、私も合同会社NOMIELというIT系のデジタルコンテンツ制作会社を経営しており、そこでは日常的にAIを活用していますが、特にプログラミングやコーディングの作業では圧倒的な効率化を実感しています。
本当にプログラミング言語をそこまで深く知らなくても、簡単なプログラムならAIで一瞬で作れてしまう時代になったのです。
プログラミングだけじゃない!全科目での高速学習時代
この「高速学習」はプログラミングに限った話ではありません。
1年、2年前まではあまり得意ではなかったのですが、最近のAIは数学、化学、物理といった理系科目もかなりできるようになってきています。
「生成AI」という名前からもイメージしやすいと思いますが、もともと文系科目は得意でしたから、使い方によっては多くの科目で高速学習が可能になってきているのです。
60日で2年分の学習!海外の驚きの事例
さらに驚くべき事例があります。
ナイジェリアで英語教育にAIを活用したプログラムでは、なんと60日間で2年分の学習が進んだという結果が報告されています。
60日、つまりわずか2ヶ月で本来2年間かけて学ぶ内容を習得してしまったのです!
しかも注目すべきは、そのプログラムが終わった後の学年末テストでも、これらの生徒たちは高得点を取っていたという点です。
つまり、単に詰め込んだだけではなく、AIとの対話を通じて学ぶスキルそのものを身につけた生徒は、他の分野でも自分で学習を進められるようになったということなのです。
これは「学び方を学んだ」という、まさに理想的な教育の形と言えるでしょう。
AIの使い方で結果は180度変わる
すべてのAI活用が成功するわけではない
ここまで聞くと「じゃあAIさえあれば誰でも学習が加速するんだ!」と思われるかもしれません。
しかし、実はそう単純な話ではないのです。
オランダの大学で行われた別の研究では、同じようにプログラミングのコースでAI支援を受けた学生と、受けなかった学生を比較しました。
その結果は…どちらのグループもあまり差がなかったのです。
「あれ? 効果がないの?」と思いますよね。でも、結果をもう少し詳しく見てみると、重要な発見がありました。
成績が上がる使い方、下がる使い方
AI を使ったグループの中でも、使い方によって成績が上がっているグループと下がっているグループに明確に分かれていたのです。
その違いは何だったのか?
成績が上がったグループの特徴:
- 「考え方を教えてください」
- 「説明してください」
- 「なぜこうなるのですか?」
こういった質問をAIに投げかけていました。
成績が上がらなかったグループの特徴:
- 「答えを書いてください」
- 「この問題の答えは何ですか?」
単純に答えだけをもらっていたのです。
塾講師が大切にしていることと同じ
この結果を見て、私たち塾講師はすぐにピンと来ました。
これって、私たちが普段から生徒に対して意識していることと全く同じなんです!
私たちは常に「答えを教えるんじゃなくて、考え方を教える」「プロセスを理解させる」ことを重視してきました。
答えだけ与えると、その場しのぎにはなるかもしれませんが、本当の理解には繋がりません。長期的な目線で見たときの成績アップには絶対につながらないのです。
正しいAIとの付き合い方を教える必要性
だからこそ、家庭や学校、塾などで大人が「AIとの正しい付き合い方」を教える必要があるのです。
正しい向き合い方ができれば、AIは最強のツールになることは間違いありません。
この記事を読んでいる方で、もし普段の学習にAIを使っている人がいたら、答えだけをもらうような使い方になってしまっていないか、今の自分の使い方について考えるきっかけにしてもらえればと思います。
先生の役割は「ティーチング」から「コーチング」へ
先生をサポートするAIの登場
AI時代に先生の役割はどう変わっていくのでしょうか?
実は、個別指導をしている先生にAIでサポートをさせたという海外の事例がすでに存在します。
どういうサポートかというと──
- 生徒が間違えたときに「どういう手順で解説するか」
- 問題につまったときに「どういうヒントを出せばいいか」
こういったことをAIがサジェストするのです。
つまり、先生が生徒に教える前に、AIが先生にアドバイスをするという仕組みです。
結果はどうだったか?
AI支援を受けた先生の生徒は、受けなかったグループより課題達成率が高くなったのです。
先生をサポートすることにもAIは効果的に使える──これは、塾講師の立場からすると「AIの方が教え方がうまい!?」という何とも言いにくい結果ではありますが…
もちろん、優秀な講師と新人講師ではAI支援の影響の幅は全然変わってくると思いますし、一概には言えません。
ティーチングとコーチングの違い
しかし、この事例から見えてくるのは、**これからの先生に求められるのは「ティーチング」よりも「コーチング」**だということです。
ティーチングとは?
- 知識を教えること
- 解き方を説明すること
- 情報を伝達すること
しかし、これらは言ってしまえばChatGPTが24時間いつでも教えてくれる時代になりました。
コーチングとは?
- 生徒の考えや悩みに寄り添うこと
- どこに向かっていくかをアシストすること
- モチベーションを高めてあげること
これこそが、人間にしかできない部分なのです。
人間的な関わりこそが教育の本質
私たちニードモアアカデミーでも、普段の指導でただ問題の解き方を教えるだけでなく、その子の性格や理解度を見ながら声かけをしています。
同じ内容でも、子どもによって伝え方を変えたりするのです。
これがまさに「コーチング」です。
AIには、その子の表情を読み取って「今つまずいてるな」って気づいたり、落ち込んでる子を励ましたりする、そういう人間的な部分はまだまだできません。
もちろん、それっぽいことはできますが、そもそもAIには感情がないので、どこまでいっても、それは作り出された「感情っぽいもの」でしかないのです。
厳しいけれど現実的な話
逆に言えば、知識を教えるだけの先生は、AIに取って代わられる可能性もあるということです。
厳しいですが、これは現実として受け止める必要があります。
だからこそ私たち塾講師も、常に**「自分にしかできないことは何か」**を考えていかないといけないのです。
ニードモアアカデミーのAI時代への取り組み
完全対人型個別指導の価値
ニードモアアカデミーは完全対人型の個別指導塾です。完全に人間の講師が教える形をとっています。
「AIを取り入れてないってことは古いんじゃないか」と思われる方もいるかもしれません。
しかし、私たちの考えは違います。
AIができること、人間にしかできないこと
確かに、知識の伝達はAIにもできます。
でもニードモアがずっと大切にしてきたのは、一人ひとりの生徒と向き合うことなんです。
- 生徒の性格
- 家庭環境
- その日の表情や様子
こういったものも含めて理解した上で指導する。
例えば、この子は今部活で悩んでいるな、家庭で何かあったのかな──そういうのを察知して声をかける。
これってAIにはできませんよね。人間同士だからこそできることです。
AIをツールとして活用する姿勢
ただし、だからといってAIを全く使わないというスタンスでもありません。
これほど便利で最強のツールは他にないのですから。
実はニードモアでも、これからの時代に向けてAI技術を使った成績分析システムや教材生成のシステムを整備していっています。
例えば、生徒のテスト結果をAIで分析して、弱点を可視化するようなシステムです。
まだ完成したシステムとして周知して使う段階ではありませんが、実は私たちは裏で自分たちの指導スキルアップや進路指導に役立てるために、部分的にすでにAIを活用しています。
両輪のバランスが重要
AIは「ツール」として活用して、でも最終的に生徒と向き合うのは人間の講師。
この両輪が大事だと私たちは考えています。
AIと人間が協力する──これがこれからの教育のあり方です。
AIに任せられることはAIに任せて、私たちはより生徒に寄り添った指導に時間を使う。これがこれからの塾の良いあり方なんじゃないかと思っています。
保護者の方へ──お子さまのAI活用をどうサポートするか
禁止するのは現実的ではない
保護者の皆さんに向けてお伝えしたいのは、今の時代、お子さんがAIを使うことを禁止するのは現実的ではないということです。
学校でも普通に使い始めていますし、社会全体でAIの活用が進んでいます。
正しい使い方を教えることが大切
大事なのは、正しい使い方を教えることです。
先ほどお話ししたように、答えだけを聞くんじゃなくて、考え方を聞く。説明してもらう。
自分で考えるプロセスを大切にする──これが何より重要です。
批判的思考力の育成
そして、AIの答えを鵜呑みにしないこと。
AIも間違えることがあります。だから「本当にこれ合ってるかな?」って疑う力も必要なんです。
これは情報を批判的に見る力、クリティカルシンキングと呼ばれるものです。
自分にしかできないことを見つける
もう一つ追加で大事だと思うのが、自分で本当にやりたいことを見つけることです。
当たり前ですが、AIができることはAIがやってくれる時代になるわけです。
そうなったときに大事なのは、人間である「自分にしかできないこと」「自分が本当にやりたいこと」を見つけることなんですよね。
いろんな経験をさせてあげる
保護者の皆さんには、お子さんにいろんな経験をさせてあげてほしいと思います。
子どものうちからいろんなものに触れさせてあげることが大切です──スポーツでもいいし、読書でもいいし、音楽でも美術でも。
そういう中から「これ好きだな」っていうものを見つけることが、後々はAI時代を生き抜く力にもなるのです。
まとめ
今回の内容を整理すると、以下のようになります。
AI時代の学習革命
- AIによって学習スピードは確実に上がっている
- 60日で2年分の学習が進むような事例も実際に存在する
- プログラミングだけでなく、多くの科目で高速学習が可能に
使い方で天と地ほどの差が出る
- AIをただ与えるだけでは効果は出ない
- 答えを聞くのではなく、考え方や説明を求める使い方が重要
- 正しい使い方を大人が教える必要がある
先生の役割の変化
- 知識を教える「ティーチング」から、生徒に寄り添う「コーチング」へ
- AIには表情を読み取る、励ます、共感するといった人間的な部分はできない
- 知識を教えるだけの先生はAIに取って代わられる可能性がある
ニードモアの姿勢
- 完全対人型個別指導の価値を大切にしながら
- AIをツールとして裏側で活用
- 人間とAIの協力こそがこれからの教育のあり方
保護者へのメッセージ
- AIの使用を禁止するのではなく、正しい使い方を教える
- 批判的思考力を育てる
- 自分にしかできないことを見つけられるよう、いろんな経験をさせる
次回予告
今回は「AI時代の学び方革命」のPart1として、AIがもたらす変化と先生の役割について語りました。
次回はもっと具体的なAI活用法や、実際にどう勉強に取り入れていけばいいのかという実践編をお届けします!
学生の皆さんが今の学習に直接活用していけるノウハウを詳しく解説しますので、ぜひ次回もお聴きください!
私たちニードモアアカデミーは、AI時代においても変わらず、一人ひとりの生徒に真剣に向き合い続けます。
そして同時に、時代に合わせた最適なツールを取り入れながら、お子さまの未来をサポートしていくことをお約束いたします!
ニードモアの『聴く塾便り』はYoutube、Spotify、Apple Podcasts、Amazon Musicで配信中です。
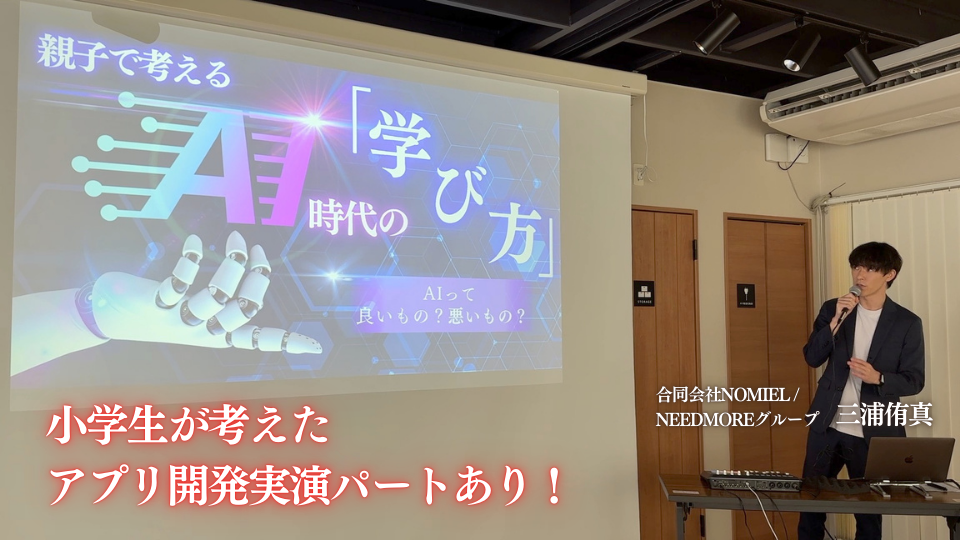
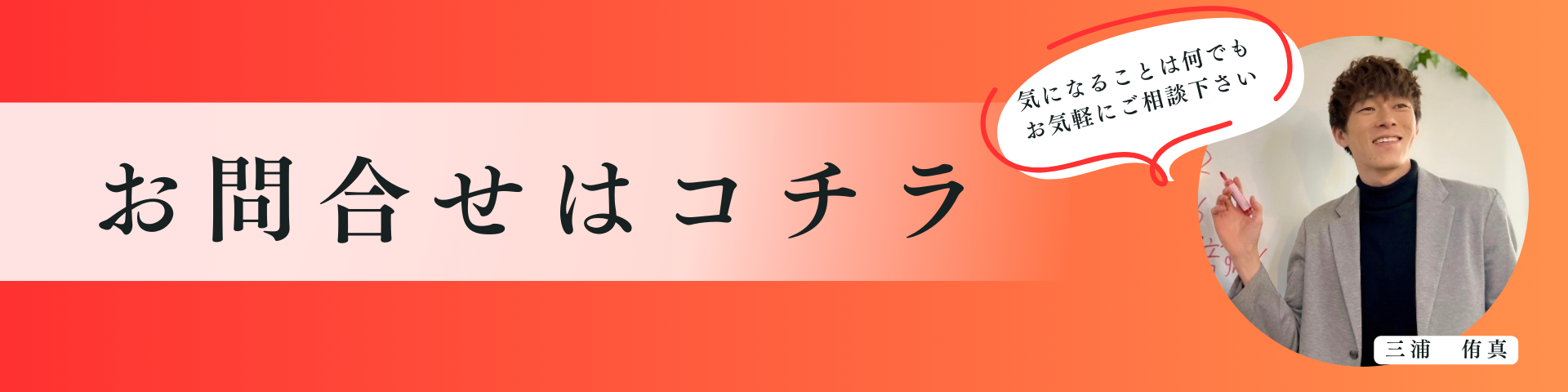

コメント