こんにちは、兵庫県加古川市・播磨町で学習塾「ニードモアアカデミー」を運営している三浦です。
いよいよ「今この時代に勉強が必要な理由」シリーズの最終回となりました。
これまで3回にわたって、第1回では「10年後も通用する人材になるために今身につけるべき力」、第2回では「生きる力の正体」としての問題解決能力、第3回では「自分で学ぶ力」の重要性についてお話ししてきました。
最終回となる今回は「保護者が知っておくべき『これからの教育』のポイント」として、これまでの内容を踏まえて、実際に家庭でどんなサポートができるのかを具体的にお話しします。
これまでの内容の要点整理
シリーズで伝えてきた3つのポイント
まず、これまで3回でお話ししてきた内容を簡潔に整理したいと思います。
1つ目:これからの時代に必要な力は問題解決能力
AI時代でも、いやAI時代だからこそ、創造的思考、柔軟性、好奇心といった人間らしい能力が重要になる。そしてそれらを統合した「問題解決能力」こそが生きる力の正体だということ。
2つ目:日々の勉強がその力を鍛えている
課題設定、情報収集・分析、解決策立案、実行、検証・改善という問題解決のプロセスを、定期テスト対策や受験勉強、各教科の学習を通じて自然に身につけているということ。
3つ目:主体性が全ての土台
やらされる勉強では真の力は身につかない。本来人間が持っている「知りたい」という欲求を引き出し、内発的動機に基づく学習に転換することが重要だということ。
保護者に一番意識してもらいたいこと
この3つのポイントを理解していただいた上で、保護者の方ができることを考えていきます。
ここで保護者の方に一番意識してもらいたいのは**「環境を整える」**ということなんです。
従来の教育観からの脱却
過去の成功体験が通用しない時代
まず最初に、保護者の皆さんにお伝えしたいのは**「従来の教育観を見直す必要がある」**ということです。
多くの保護者の方が、ご自身の学生時代の成功体験をベースに子どもの教育を考えがちなんですね。
「私たちの時代は、とにかく暗記して、問題集を何回も解いて、偏差値の高い学校に行けば将来安泰だった」
でも、第1回でお話しした通り、今の子どもたちが大人になる頃の社会は、我々の時代とは全く違います。
過去の成功法則が通用しない時代になってきているのです。
視点を「結果」から「プロセス」へ
だから**「いい点数を取れば安心」「いい大学に行けば大丈夫」という発想から、「どんな力を身につけているか」「どんな学び方をしているか」に視点を移す**必要があるんです。
例えば中学校の数学のテストで子どもが90点を取って帰ってきたときも、結果だけでなく、そこに至るまでの過程を大切にするということですね!
プロセスの価値を認める
例え80点だったとしても、「自分で計画を立てて、間違いから学んで、改善策を考えた」なら、それは100点より価値のある学習だと捉える。
この視点の転換ができるかどうかが、これからの時代の子育ての分かれ目だと思います。
家庭でできる具体的なサポート
大前提:保護者は「指導者」ではない
具体的に、家庭ではどんなサポートができるのでしょうか。
大前提として、勉強を教えるのは学校の先生や塾の講師の役割で、指導部分に関してはそこにある程度任せてしまってもいいかなと思うんですね。
保護者の方は子どもが学びやすい環境や雰囲気を作ることが最も重要なんです。
サポート①:関心を示す
まず1つ目が**「関心を示す」**ことです。
家庭での会話を「管理」から「関心」に変えるんです。
子どもの学習を監視するのではなく、興味を持って聞くということですね。
そして子どもが疑問を持った時は、一緒に驚いてあげる。
「なんで英語にはTheがあるの?」
こういう質問が出た時に、「面白いこと考えるね!」「一緒に調べてみる?」と共感を示す。
サポート②:結果よりプロセスを見る
2つ目が**「結果よりプロセスを見る」**ことです。
テストで点数が悪かった時に叱るのではなく、まず子どもの気持ちを受け止める。
「悔しかったね」「頑張ったのに残念だったね」と共感してから、「何か手伝えることある?」と聞く。
子ども自身が考えるのを待つということですね。
サポート③:学びを応援する姿勢を見せる
そして3つ目が**「学びを応援する姿勢を見せる」**ことです。
どんな形でも構いません!
子どもたちにとってお父さん、お母さんは敵ではなく常に一番の味方であって欲しいのです!
重要:すべてを解決してあげようと思わない
ここで大切なのは、保護者の方が**「すべてを解決してあげよう」と思わない**ことです。
子どもが困っている時に、答えを与えるのではなく**「一緒に考える」と言う姿勢でいることが重要**なんです。
「お母さんもよくわからないけど、調べてみようか」 「お父さんの経験だとこんなことがあったよ」
と、あくまで対等な立場で関わる。
教える必要はないんです。興味を持って、応援して、環境を整えてあげる。それが保護者の方の一番大切な役割だと思います。
デジタル時代の家庭学習環境
デジタル=悪ではない
デジタルツールとの付き合い方は、多くの保護者の方が悩まれている部分ですね。
まず大前提として**「デジタル=悪」ではない**ということを理解していただきたいんです。
問題なのは**「受動的な使い方」**です。
- YouTubeをただ見続ける
- ゲームをただやり続ける
これは確かに学習にはなりません。
能動的な使い方なら最強の学習パートナー
でも**「能動的な使い方」なら、デジタルツールは最強の学習パートナーになります。**
能動的な使い方の例:
- 授業で習った内容について「もっと詳しく知りたい」と思った時に、信頼できるサイトや動画で調べる
- わからない問題があった時に、解説動画を見て理解を深める
- 興味のある分野について、専門家の講義動画を視聴する
こういう使い方なら、デジタルツールは学習を大いに促進します。
使い方次第で、毒にも薬にもなるということですね。
保護者がすべきは「禁止」ではなく「正しい使い方の指導」
だから保護者の方がすべきなのは**「禁止」ではなく「正しい使い方の指導」**なんです。
「この情報は信頼できそう?」 「他の情報源でも確認してみよう」 「なぜそうなるかまで調べてみよう」
こうやって情報リテラシーを育てながら、デジタルツールを学習の味方にしていく。
学習記録の習慣をつける
そして重要なのは**「学習記録」の習慣**です。
「今日学んだこと」「まだわからないこと」「明日調べたいこと」をノートやデジタルツールで記録する習慣をつける。
自分の学習を客観視する力が身につきますね。
これができると、子ども自身が自分の成長を実感でき、学習への意欲が継続するんです。
長期的な視点での子育て
20年後、30年後を見据える
最後に、保護者の皆さんに一番お伝えしたいのは**「長期的な視点を持つ」**ことの大切さです。
目の前のテストの点数や、今の成績に一喜一憂するのではなく、「この子が20年後、30年後にどんな大人になってほしいか」を考えてほしいんです。
変化の激しい時代を生き抜くために必要なのは、特定の知識ではなく**「学び続ける力」**です。
だから今大切なのは、子どもが「学ぶことが楽しい」「新しいことを知るのが面白い」と感じられるかどうかなんです。
目先の結果よりも、学習に対する姿勢や態度を重視するということですね。
塾講師も同じ考えで取り組んでいる
そして、これは我々塾講師も同じ考えなんです。
もちろん目の前の成績向上も大切ですが、それ以上に**「この子が将来、自分で問題を解決していける力を身につけているか」を常に意識しています。**
だからこそ、家庭と塾が同じ方向を向いて、同じ価値観で子どもをサポートすることが重要なんです。
家庭と塾の連携が子どもの成長の鍵
家庭と塾の連携が、子どもの成長にとって大切だということですね。
塾では学習の技術的な部分をサポートし、家庭では学習への動機や興味を育てる。
この両輪がうまく回ることで、子どもたちは真の意味での「生きる力」を身につけていくことができるんです。
まとめ
さて、ここまで4回にわたってお話ししてきた「なぜ今勉強するのか」シリーズ、いかがでしたでしょうか?
後から見返すと内容が重複してしまっている部分もあったので、構成をもっとしっかりしておくべきだったと少し反省しています…(^_^;)
でも我々自身も改めて、教育の本質について深く考える機会になりました。
このシリーズを通じてお伝えしたかったのは、勉強は単なる知識の詰め込みではなく、人生を生き抜くための「問題解決能力」を育てる最高の機会だということです。
そして、その力を最大限に引き出すためには、やらされる勉強ではなく、子ども自身の興味と主体性に基づく学習が必要だということです。
ニードモアでも保護者の皆さんと一緒に、子どもたちの可能性を最大限に引き出していきたい思います!!
ニードモアの『聴く塾便り』はYoutube、Spotify、Apple Podcasts、Amazon Musicで配信中です。
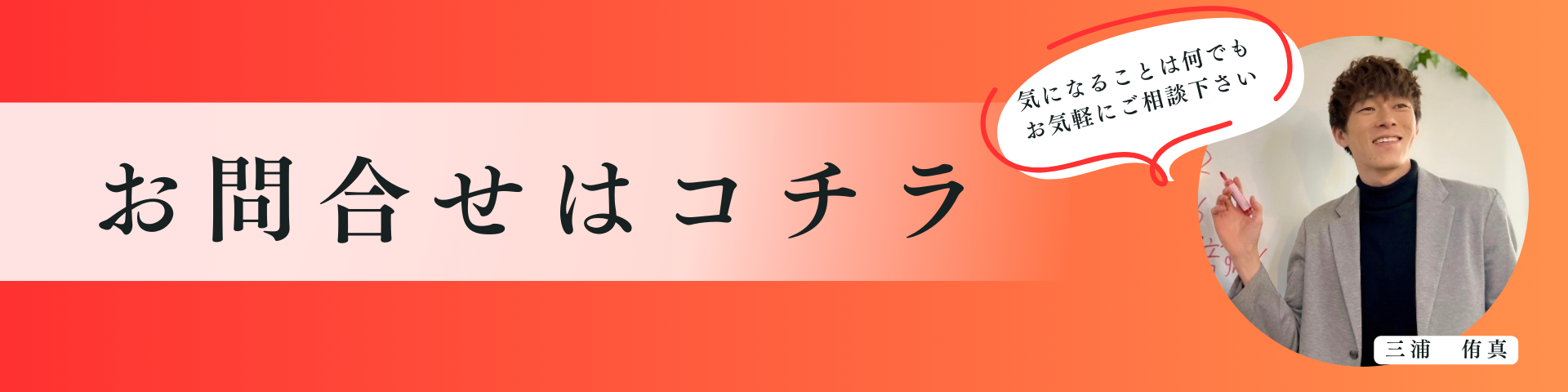

コメント