こんにちは、兵庫県加古川市・播磨町で学習塾「ニードモアアカデミー」を運営している三浦です。
前回の配信では「生きる力の正体」として、問題解決能力を具体的に分解し、日々の勉強が将来にどう役立つのかをお話ししました。
しかし、「問題解決能力が大切なのはわかったけど、そもそも勉強に興味が持てない子はどうすればいいの?」という疑問を持たれた方も多いのではないでしょうか。
第3回となる今回は「なぜ今の子どもたちには『自分で学ぶ力』が必要なのか」として、学習への興味を引き出し、主体性を育てる具体的な方法についてお話しします。
現代の子どもたちが置かれた環境
情報の爆発的増加がもたらした変化
なぜ今の時代に「自分で学ぶ力」がこれほど重要なのでしょうか。
一番大きな変化は情報の爆発的増加です。
昔は学習における情報源と言えば:
- 教科書に書いてあることを覚える
- 先生が教えてくれることを身につける
これが学習のメインでした。
しかし今はスマホ一台で世界中の情報にアクセスできる時代です。YouTubeで大学レベルの授業も見れるし、AIに質問すれば瞬時に答えが返ってきます。
情報過多がもたらす新たな課題
情報が多すぎることで、逆に「何をどう学べばいいかわからない」という状況に陥る子どもたちが増えています。
だからこそ以下の力が必要になってきます:
- 自分にとって必要な情報は何か
- どの情報が信頼できるのか
- どう学習すれば効果的か
これらを自分で判断する力が求められているのです。
前回お話しした問題解決能力のステップで言えば、「課題設定」と「情報収集・分析」の部分にあたります。
実社会では課題設定から自分で行う
学生である今は、課題を与えられてそれをこなすという流れが中心です。
しかし実社会では課題設定から自分でしないといけない場面がほとんどなのです。
与えられた限られた情報だけを使っている人と、自分自身で情報をキャッチして活用し、学習・スキルアップしている人では能力の差が生まれることは当然です。
そういった意味でも、現代の子どもたちが置かれた状況は昔と比べてもより一層「自分で学ぶ力」が必要だと言えます。
「やらされる勉強」の限界
なぜ多くの子どもが勉強に興味を持てないのか
多くの子どもたちが勉強に興味を持てない最大の要因は、「やらされる勉強」になってしまっていることです。
「テストがあるから覚えなさい」
「入試に出るから解きなさい」
「宿題だからやりなさい」
これって全部外発的動機、つまり外から与えられた理由で勉強している状態なんです。
外発的動機と内発的動機の違い
外発的動機だけの学習の特徴:
- 興味が長続きしない
- 深い理解につながりにくい
- やらされている感が強い
一方で内発的動機から始まる学習の特徴:
- 「これ面白い!」
- 「もっと知りたい!」
- 「なぜそうなるんだろう?」
このような内発的動機から始まる学習は、集中力も記憶の定着も格段に良くなります。
興味があることは自然と覚えてしまうものです。
目指すべき方向性
だから我々が目指すべきは「やらされる勉強」から「やりたい勉強」への転換なのです。
興味を引き出すために必要な視点転換
根本的な勘違い
「どうやって勉強への興味を引き出せばいいのか?」
多くの人が「興味を持たせる方法」を探しがちですが、実はそこに根本的な勘違いがあります。
興味って「持たせるもの」じゃなくて、「本来あるものを阻害している要因を取り除く」ものなんです。
人間には生まれつき学習欲求がある
人間には生まれつき「知りたい」「理解したい」という欲求があります。
その証拠:
- 赤ちゃんが何でも口に入れたがる
- 子どもが「なんで?なんで?」って質問攻めする
子どもは本来好奇心旺盛なのです。
なぜ中学生になると「勉強つまらない」と言うのか
じゃあなぜ中学生になると「勉強つまらない」って言うようになるのか?
それは学習の「目的」と「手段」が逆転しているからなんです。
本来の姿:
- 数学:世界の法則を理解する「手段」
- 英語:他文化とコミュニケーションを取る「手段」
逆転した姿:
- 数学:テストで点を取る「目的」
- 英語:受験に合格する「目的」
手段が目的化してしまうと、本来の面白さが見えなくなってしまいます。
本来の学問の面白さを伝える
だから必要なのは「本来の学問の面白さ」を伝える、というか分かってもらうことなんです。
例:歴史の学び方
❌ 年号の暗記が目的 → つまらない
⭕ 以下のような本質に触れる:
- 人間がどうやって今の社会を作り上げてきたのか
- 過去の人たちの試行錯誤から何を学べるのか
本質に触れれば、これほど面白い学問はないのです。
デジタル時代の学習法
現代ならではの「自分で学ぶ」環境の作り方
現代ならではの「自分で学ぶ」環境の作り方について触れておきたいと思います。
デジタルツールはうまく活用できたほうが良いです。
すぐ調べられる環境を活用する
例えば、疑問が湧いた時にすぐ調べられる環境を作りましょう:
- 学校で習った公式について、なぜこの公式を使うのかの理由まで調べる
- 日常で目の当たりにする何気ない現象について調べる
現代においてそういったすぐ調べられる環境は既に整っている家庭がほとんどだと思うので、あとは習慣とやり方です。
保護者ができるサポート:正しい調べ方を教える
保護者の方がサポートしていただく場合は、正しい「調べ方を教えてあげる」ことが重要です:
- 「この情報は信頼できるか?」
- 「他の情報源でも確認してファクトチェックしてみる」
- 「なぜそうなるかまで調べてみよう」
これにより情報リテラシーも同時に身につきます。
そしてこれがうまく作用すると、「やらされる勉強」から「知りたい勉強」への転換点にもなり得ます。
興味を「持たせる」のではなく、「本来持っている興味を引き出す」という部分ですね。
学習の記録をつける習慣
学習の記録をつける習慣も結構大切です:
- 「今日わかったこと」
- 「まだわからないこと」
- 「明日調べたいこと」
こうやって学習を可視化することで、自分の成長が実感でき、次への意欲につながります。
これは自己管理能力も育てられます。
これらの習慣が身につけば、もう「やらされる勉強」からは完全に脱却できるはずです。
まとめ
今回は「自分で学ぶ力」の重要性と、その育て方について詳しくお話ししてきました。
重要ポイント:
- 情報過多の時代だからこそ「自分で学ぶ力」が必要
- 「やらされる勉強」から「やりたい勉強」への転換がキー
- 興味は「持たせる」のではなく「引き出す」もの
- 学習の「目的」と「手段」の逆転を正す
- デジタルツールを活用し、情報リテラシーを身につける
前回お話しした問題解決能力も、この主体性があって初めて本当に身につきます。
誰かに言われてやる問題解決と、自分から進んでやる問題解決では、身につく力が全然違うのです。
次回は最終回となる第4回「保護者が知っておくべき『これからの教育』のポイント」です。
これまで3回にわたってお話ししてきた内容を、保護者の皆さんが実際にどう活用すればいいのか、具体的なサポート方法をお伝えします。
お子さまの「知りたい!」を引き出す環境づくりを、一緒に考えていきましょう!
ニードモアの『聴く塾便り』はYoutube、Spotify、Apple Podcasts、Amazon Musicで配信中です。
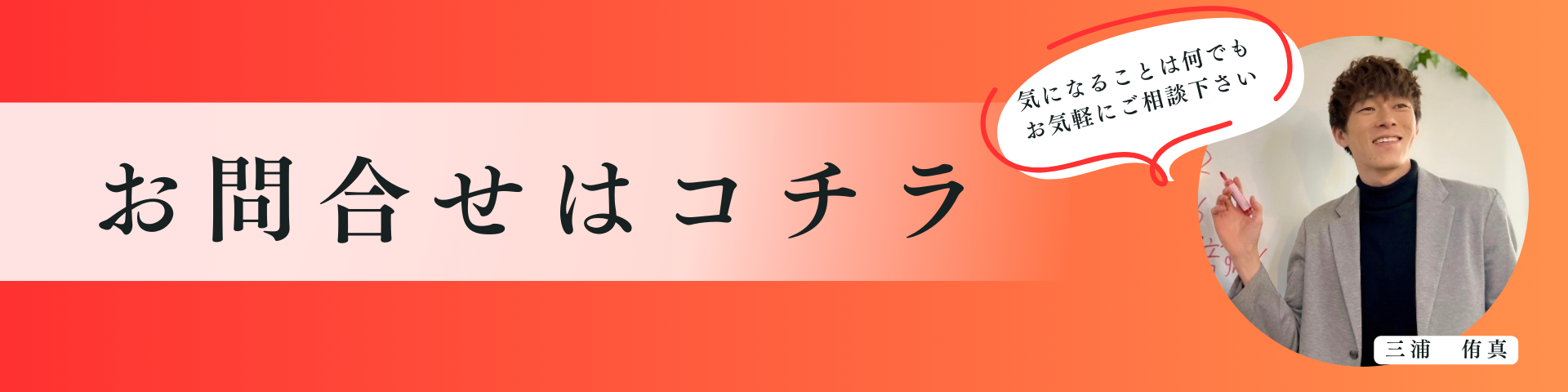

コメント