こんにちは、兵庫県加古川市・播磨町で学習塾「ニードモアアカデミー」を運営している三浦です。
前回の配信では、AI時代に学び方がどう変わるのか、先生の役割がティーチングからコーチングへと変化していくという話をしました。
そして今回は、**「で、結局どう使えばいいの?」**という疑問にお答えする実践編です!
単に答えを聞くだけではダメだということは前回お伝えしましたが、では具体的にどう活用していけばいいのか。どんなシーンで使えるのか。学年によって使い方は変わるのか。
そして、ニードモアアカデミーとしてこれからAIをどう活用していく予定なのか──2回シリーズの最終回となる今回は、そんな実践的な内容を詳しく解説していきます!
最重要スキル!効果的な質問の仕方「プロンプトエンジニアリング」
「この問題の答え教えて」はNG
まず一番大事なのが、前回も触れた**「質問の仕方」**です。
わからない問題があったとき、多くの学生が「この問題の答えは?」と聞いてしまいがちです。
例えば、宿題の数学の問題でとりあえず提出しないといけないから、「この問題の答えは?」と聞いてしまう。
しかし、これでは答えはわかっても理解はできません。
プロセスを聞く質問術
では、どう質問すればいいのか?
正しい質問の仕方:
- 「この問題の解き方を、ステップバイステップで説明してください」
- 「なぜこの公式を使うのか教えてください」
- 「この問題を解く際の考え方を教えてください」
プロセスを聞くことが重要なのです。
さらに効果的にする魔法の一言
さらに言うと、こんな付け加え方も効果的です:
- 「中学2年生にもわかるように説明してください」
- 「小学生レベルの知識だけを使って説明してください」
- 「数学が苦手な人にもわかるように優しく教えてください」
質問を工夫するだけで、返ってくる答えのレベルが劇的に変わるんです!
プロンプトエンジニアリングとは?
これを**「プロンプトエンジニアリング」**と言います。
AIに対する質問文のことを「プロンプト」と言い、そのプロンプト次第で与えられる答え方が大きく変わってきます。
つまり、どう質問するかがすごく重要なスキルになるということです。
これは学生の皆さんにもぜひ意識してほしいポイントです!
シーン別!具体的なAI活用例
では、具体的にどういうシーンでAIを使うと効果的なのか、いくつか紹介していきます。
1. わからない問題の解説を聞く
これは一番イメージしやすく、実際にもう使っている子たちも多いでしょう。
具体例:
少し複雑な二次方程式の問題でxの値を求めないといけないけど、解き方が分からないとき──
「この問題の解き方を基本から途中式も含めて教えてください」
と聞くと、AIが段階的に説明してくれます。
さらに深掘りする追加質問
もし説明を読んでもまだわからないというときは?
「今の説明のこの部分がまだわかりません。もっと簡単に説明してください」 「もっと詳しく説明してください」
追加で質問すればいいのです。
いつでも何度でも聞けるのがAIのいいところです。
自分の好きなタイミングで何度も同じことを聞くというのは、人間の先生だとなかなか難しいですからね。
ハルシネーションに要注意!
ただし、ここで覚えておいてほしいのが、前回も少し触れましたがAIの答えは100%正しいとは限らないということです。
理系科目も得意になってきているとは言え、肌感覚ではまだまだ普通にミスして間違った答えを言ってくることがあります。
AIが間違った嘘の答えを自信満々に言ってくることを**「ハルシネーション」**と言います。
常にこのハルシネーションを疑いながら、上手く付き合っていってほしいですね!
2. 英作文や小論文の添削
これも非常に効果的な活用法です。
使い方:
英作文で「この英作文を添削して、文法ミスや不自然な表現を指摘してください」と送ると、どこが間違っているか教えてくれます。
しかも質問すれば「なぜこれが間違いなのか」も説明してくれるので、ただ正解を教えてもらうよりもずっと学びになります。
小論文の場合、正解不正解というところではありませんが、より良い表現方法のアイデアをくれたりします。
この使い方は、作文力も同時に鍛えていけます。
3. 学習計画の作成
これはあまり思いつかない部分かもしれませんが、実は非常に便利な活用法です!
具体例:
「数学の定期テストまで2週間あります。関数が苦手です。1日3時間勉強できます。どういう順番で勉強すればいいですか?」
と聞くと、具体的なプランを立ててくれます。
計画立てるのって、意外と結構難しいですからね。
より精度の高い計画にするために
ただし、こういう質問だけでパッと出してもらっても、1回で思ったような答えが返ってくるとは限りません。
特に計画表を作るような作業だと、自分が求めている答えを得るためには:
- 何度か修正を加えてもらう
- 自分の今置かれている状況をもっと細かく伝える
- 次回の目標を具体的に伝える
これがまさに「プロンプトエンジニアリング」です!
AIに与える情報が多ければ多いほど、答えもそれを踏まえてくれるので、より自分にあったものになって返ってきます。
4. 英会話の練習
最近ではチャットベースだけでなく音声ベースでもAIと対話ができるようになったので、英会話の練習も可能になりました!
使い方:
「私は中学2年生です。英語で日常会話の練習をしたいので、簡単な英語で話しかけてください」
と言えば、相手になってくれます。
24時間英会話の練習相手がいるというのは、一昔前だと考えられなかったことですよね。
その他の活用シーン
ここまでいくつかシーン別の活用法を挙げてきましたが、技術は日々進化していて、今では本当にあらゆる場面で活用できるようになってきています。
ぜひご自身でも「こんな場面でも使えそう」と一度考えてみてください!
絶対にやってはいけない3つのNG行動
ここまでのパートでも出てきている話なので繰り返しにはなってしまいますが、大切なことなのでもう一度しっかりお伝えしたいと思います。
NG行動①宿題をそのまま丸投げする
「この宿題全部やって」と頼んで、出てきた答えをそのまま写す──これが一番すぐに思いつくダメな使い方ですね。
これをやってしまうと:
- 全く力がつかない
- 宿題は一応完成できても定期テストになったら何もできなくなる
- 学習習慣が身につかない
宿題の目的は「提出すること」ではなく「理解すること」「定着させること」です。
NG行動②AIの答えを鵜呑みにする
前述したハルシネーションの問題です。
AIも間違えることがあるので、「本当にこれ合ってるかな?」と疑う姿勢が大事です。
対策方法:
- 教科書と照らし合わせてみる
- 複数の情報源で確認する
- わからない場合は先生に確認する
これは情報リテラシーの教育にもつながる大事なポイントです。
現代社会では、インターネット上に無数の情報があふれています。その中から正しい情報を見極める力は、学習だけでなく人生全般において必要なスキルなのです。
NG行動③考えることを放棄する
わからない問題があったとき、すぐAIに聞くのではなく:
- まず自分で数分でも考えてみる
- 教科書を見返してみる
- それでもわからなかったらAIに聞く
反射的にAIに頼るのではなく、自分で考える時間もちゃんと持つということです。
すぐ答えを求めるクセがつくと、考える力が育たなくなってしまいます。
学生時代は特に、AIは「最後の手段」くらいに思っておいても良いかもしれません。
学年別!最適なAI活用法
では、学年別にどういう使い方がおすすめか、具体的に見ていきましょう。
小学生:まだAIに頼りすぎない方がいい
ここまでAIの話をしてきましたが、実は小学生の段階では、まだガッツリ使いすぎない方が良いと考えています。
理由:
小学生のうちは、基礎学力をしっかり身につける時期です。
- 自分で考える習慣
- わからないことを人に聞く力
- コミュニケーション能力
これらを育てる方が優先度が高いのです。
推奨される使い方:
もちろん、これからの時代に向けて存在やある程度の正しい使い方を習得しておいて損はありません。
ただし使うとしても、保護者の方と一緒に使うのがいいでしょう。
練習という意味も含めて、親子で一緒にAIと対話してみる。これなら安心です。
中学生:本格的な活用開始
中学生になると、もう少し本格的に使っていいと思います。
推奨される使い方:
- 問題の解説を聞く
- 英作文の添削をしてもらう
- 暗記のコツを聞く
- 学習計画を立ててもらう
ただし、使い方は周りの大人がある程度はチェックしてあげた方がいいかなと思います。
間違った使い方をしてしまっていないか、定期的に確認することが大切です。
高校生:自由に使いながら判断力を養う
高校生になったら、もうかなり自由に使っていいと思います。
推奨される使い方:
- 大学受験の勉強
- 小論文の練習
- 専門的な内容の理解
- 志望理由書の作成サポート
高校生ならもう自分で判断していかないといけませんからね。
全学年共通の大原則
どの学年にも言えるのは、やはり**「考える力」を失わないように、すぐ答えを聞かない**という姿勢は持ち続けてほしいということです。
AIは強力なツールですが、それに依存しすぎて思考力が低下してしまっては本末転倒です。
ニードモアアカデミーの今後のAI活用構想
では、最後にニードモアとしてこれからどうAIを活用していくかという話をします。
すでに進行中のシステム開発
前回もちょっと触れましたが、ニードモアでもAI技術を使った成績分析システムや教材生成のシステムを整備していっています。
まだ完成したシステムとして導入できている段階ではありませんが、段階的に進めているところです。
1. AI成績分析システム
目的:
AIで成績データの分析をして、どの単元が弱いのかをもっと可視化できるようにしていきたいと思っています。
一目で生徒の苦手がわかるようなイメージです。
具体例:
例えば数学で言うと:
- 「関数は得意だけど図形が苦手」
- 「計算ミスが多い」
- 「文章題の読解に時間がかかっている」
こういったことがデータで出てくると、指導の方針も立てやすくなります。
今も定期テストや模試などでそういった結果を見ることはできますが、もっと深くまで分析できるニードモアのオリジナルシステムを構想しています。
期待される効果:
今以上に細かく弱点分析ができれば、そこをもっと重点的に指導していくことも可能になります。
弱点分析自体は今までも私たちがやってきたことですが、AIを正しく使うことでより効率的にできるようになるんじゃないかと考えています。
データに基づいた指導も、さらに効果が期待できるでしょう。
2. 個別教材の生成サポート
構想:
先ほどの弱点分析から「この生徒にはこのレベルの問題が必要だな」というときに、AIを活用して問題を作っていけたらいいなと考えています。
本当の意味で一人ひとりに合わせた教材ということですね。
なぜ必要なのか?
市販の問題集だと、この生徒にはちょっと難しすぎる、逆に簡単すぎる、ということがあります。
もちろん調整は可能ですが、AIを使えば、その子のレベルにぴったりの問題を用意できる可能性が高まります。
これは個別指導塾ならではのさらなる強みになりそうです!
最も大切な原則:AIは補助ツール
これも繰り返しになりますが、大事なのはAIはあくまで補助ツールだということです。
変わらない私たちの姿勢:
- 最終的に生徒と向き合うのは人間の講師
- 一人ひとりに合わせた声かけ
- モチベーション管理
- 人間的な関わり
これらは人間にしかできません。
前回も話しましたが、これはAIと人間の役割分担の問題です。
AIができることはAIに任せて、私たちはより生徒に寄り添った指導に時間を使っていく──これがニードモアのこれからの方向性です。
まとめ:AI時代の賢い学び方
2回にわたってお届けした「AI時代の学び方革命」、今回の内容を整理しましょう。
効果的なAI活用の5つのポイント
1. 質問の仕方が全て
- 答えを聞くのではなく、プロセスを聞く
- 「ステップバイステップで説明してください」
- 「中学生にもわかるように教えてください」
- プロンプトエンジニアリングを意識する
2. 活用シーンは無限大
- 問題の解説を聞く
- 英作文・小論文の添削
- 学習計画の作成
- 英会話の練習
- その他、自分で新しい活用法を見つける
3. 3つのNG行動は絶対に避ける
- 宿題の丸投げ
- AIの答えの鵜呑み(ハルシネーションに注意)
- 考えることの放棄(すぐ聞かない)
4. 学年に応じた使い方
- 小学生:保護者と一緒に、基礎学力優先
- 中学生:本格的活用、大人のチェックあり
- 高校生:自由な活用、自己判断力の育成
5. AIは補助ツール、主役は人間
- データ分析や教材作成はAIが得意
- 寄り添い、励まし、共感は人間の役割
- ニードモアも両輪で進化していく
AI時代だからこそ大切にしたいこと
技術がどれだけ進化しても、変わらない教育の本質があります。
それは**「考える力」「人と関わる力」「自分で学び続ける力」**です。
AIは確かに強力なツールです。正しく使えば学習効率は劇的に向上します。
しかし、それはあくまで「手段」であって「目的」ではありません。
目的は、お子さまが将来社会で活躍できる力を身につけること。
そのためには、AIの力を借りながらも、自分の頭で考え、人と協力し、粘り強く取り組む姿勢を育てていくことが何より大切なのです。
保護者の方へ、生徒の皆さんへ
2回にわたってAI時代の教育について話してきましたが、保護者の方も生徒さんも、何か得られるものがあったなら嬉しく思います。
もし質問や「こういう使い方はどうですか?」というようなことがあれば、塾に来たときでもLINEでも気軽に聞いてください!
私たちも日々勉強しながら、より良い指導を目指していきます。
AI時代だからこそ、人間らしい学びと、AIの便利さ、その両方を大事にしていきましょう!
ニードモアの『聴く塾便り』はYoutube、Spotify、Apple Podcasts、Amazon Musicで配信中です。
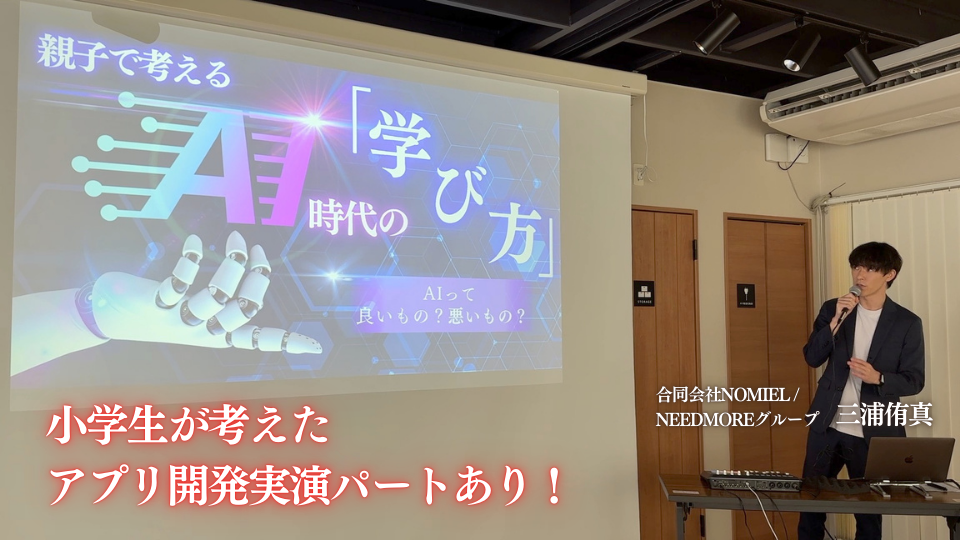
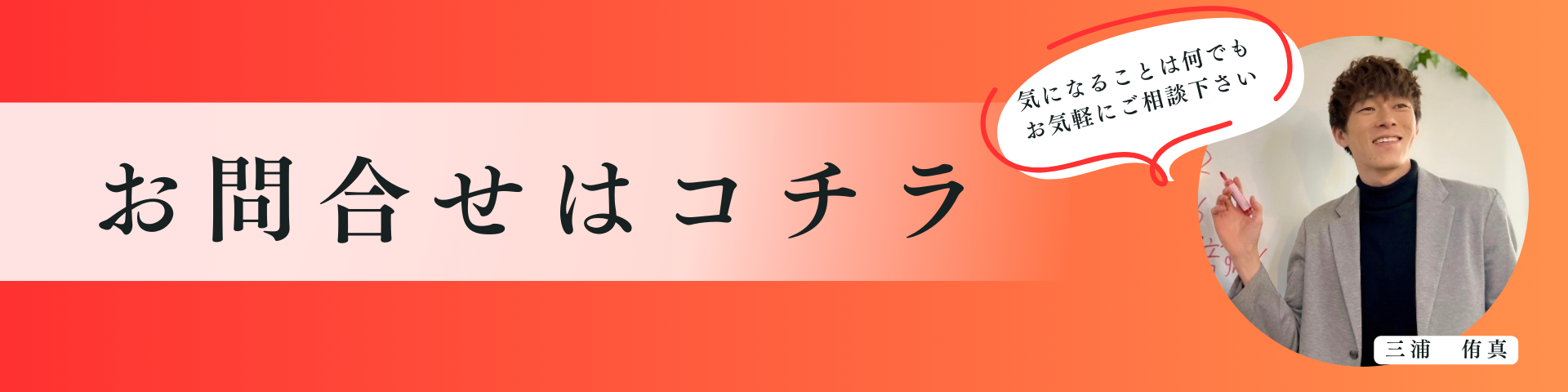

コメント