こんにちは、兵庫県加古川市・播磨町で学習塾「ニードモアアカデミー」を運営している三浦です。
夏期講習も無事に終了し、生徒たちの大きな成長を実感しています。
しかし、本当の勝負はここからです!
「受験生じゃないからまだ大丈夫」と思っている中1・中2の生徒さんや保護者の方に、ぜひ知っておいてほしい内容です。
2学期は「学習の質」が問われる
1学期との根本的な違い
2学期は1学期とは根本的に異なる能力が求められます。1学期はまだ「覚えれば何とかなる」内容が多かったのに対し、2学期からは「理解して応用する」力が必要になってくるのです。
中1数学の例:
- 1学期:正負の数や文字式(計算方法を覚えれば解ける)
- 2学期:方程式や関数(「なぜその式を立てるのか」という思考力が必要)
中1英語の例:
- 1学期:be動詞と一般動詞(単純な暗記がメイン)
- 2学期:三人称単数(主語を見て動詞の形を判断する思考プロセスが必要)
このように、2学期からはこれまで以上に「わかったつもり」が通用しなくなり、より深い理解が求められるようになります。
陥りがちな「2学期の罠」
中1生の罠:慣れによる油断
中1の2学期は「中学校に慣れた」という油断が成績に大きく影響します。1学期は緊張感があったものの、2学期になると「もう大丈夫」という気の緩みが生じがちです。
しかし実際は、2学期からが本当の中学校の勉強の始まりです。英語の三人称単数や理科の化学分野など、小学校では習わない新しい概念が続々と登場します。
重要なポイント:
- 中1の2学期の内容は高校受験で超頻出
- 1年の方程式ができないと中3の二次方程式は解けない
- 三人称単数が理解できないと高校受験の英語は厳しい
つまり、中1の2学期は「高校受験の基礎の基礎を作る時期」なのです。
中2生の罠:中だるみ
中2の2学期の最大の罠は「中だるみ」です。受験生でもなく、新入生でもない、一番気が緩みやすい時期です。
しかし、中2の2学期で学習する内容も高校受験では絶対に出題される重要分野ばかりです:
- 数学の一次関数
- 英語の比較級
- 理科の化学変化
実際、中3になって「一次関数が分からない」という生徒は毎年数多く見受けられます。
2学期を乗り切る3つの必勝法
1. その日の理解度チェック
「分かった」と「できる」は全く違います。塾の授業で分かったからといって、時間が経っても一人で同じように解けるとは限りません。
実践方法:
- 毎日、授業で習ったことを帰宅後に5分間確認する
- その日の内容を一問でも解き直してみる
- 問題の解き方を自分で説明できるかチェックする
エビングハウスの忘却曲線によると、人間は学習したことの70%を24時間で忘れてしまいます。だからこそ、当日中の復習が極めて重要なのです。
2. わからないをそのままにしない
2学期は内容が難しくなるだけでなく、進むスピードも早くなります。不明点を放置する時間は極限まで短くしましょう。
ルール:
- 今日質問できるのに「また今度」は絶対ダメ
- 分からないことはできる限りその日のうちに解決
- 雪だるま式に分からなくなることを防ぐ
ニードモアでは、自宅で使える映像教材も完全無料で提供しています。「解き方を忘れた」という時にすぐに確認できる環境を整えているので、積極的に活用してください。
3. 定期テスト対策の前倒し
1学期は2週間前の準備で間に合ったかもしれませんが、2学期は3週間、できれば1ヶ月前から準備を始める必要があります。
理由:
- 2学期の内容は理解に時間がかかる
- 丸暗記では通用しない
- より深い理解が必要
夏休みが終わった今、すでに2学期中間テストの1ヶ月前に突入していることを忘れてはいけません。
保護者の方へ:表面的な数字だけを見ないで
保護者の皆さんにお伝えしたいのは、2学期は「テストの点数という表面的な数字」だけを見ないでほしいということです。
点数だけでは判断できない理由
例えば、1学期80点だったのが2学期70点になった場合:
- 一見、成績が下がったように見える
- しかし実際は、テスト問題の難易度が高くなっただけかもしれない
- その子の実力は下がっておらず、むしろ本当の学力は上がっている可能性も
順位は比較的正確な指標になりますが、最も大切なのは「理解の深さ」です。
家庭でできる理解度チェック
もしお家でも何かできることがないかとお考えの保護者さまがおられましたら、問題の解き方や正しい答えへの辿り着き方を、子ども自身が説明できるかどうかを確認してください。これは簡単で効果的な理解度チェックの方法です。
ニードモアの授業でも、講師が教えた後に生徒に説明してもらう「立場逆転方式」を取り入れています。
今から受験を見据えて
中1・中2のうちに習慣を確立
中1・中2の皆さんには、今のうちに「勉強のやり方」を確立し、習慣として定着させてほしいと思います。中3になってから慌てて勉強法を変えても、なかなか間に合いません。
2学期を頑張る意味
今、この2学期を頑張ることで:
- 中3では基礎をある程度スキップして応用や実践問題に集中できる
- つまり、受験で周りの子たちと勝負しなければいけないタイミングになってもしっかり戦える
- 逆に甘く見ると、どんどん遅れを取ってしまう
この差は想像以上に大きいものです。
まとめ
夏期講習で培った力を無駄にしないためには、2学期の過ごし方が鍵となります。「受験生じゃないから」という考えは捨て、今この時期から高校受験を見据えた学習習慣を身につけていきましょう。
ニードモアアカデミーでは、引き続き一人ひとりの生徒に寄り添いながら、最適な学習環境とサポートを提供していきます。分からないことがあれば、遠慮なく相談してください。
次回のポッドキャストでは「中3生にとっての2学期」について詳しくお話しする予定です。ぜひご視聴ください!
ニードモアの『聴く塾便り』はYoutube、Spotify、Apple Podcasts、Amazon Musicで配信中です。
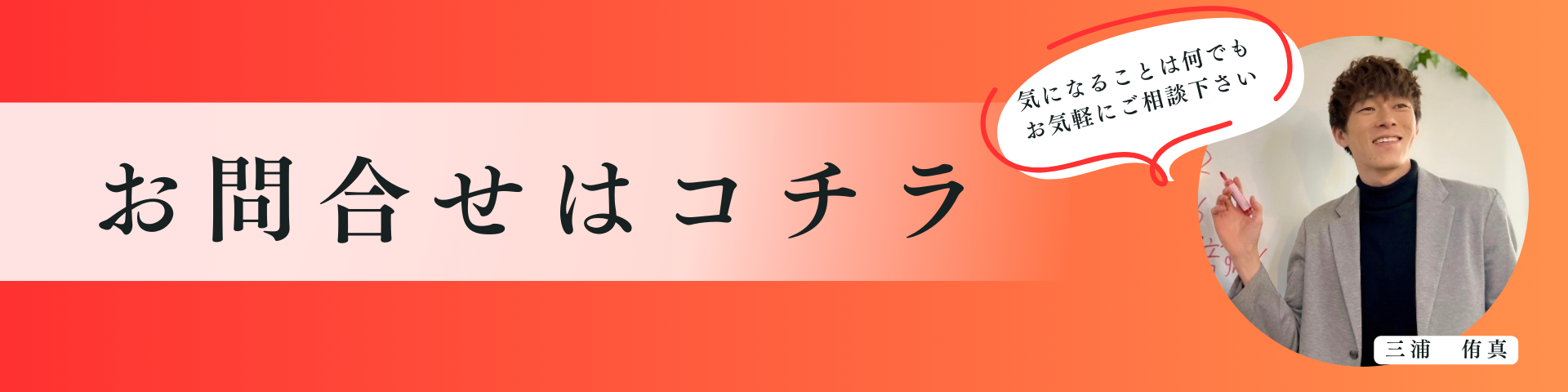

コメント